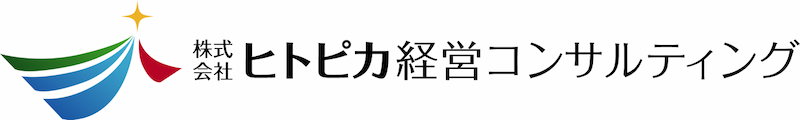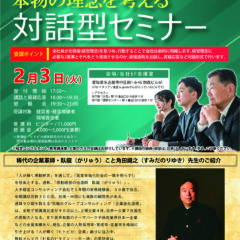Vol.119 「役職で呼ぶことは廃止しよう!」
「プライド」って、大事だが厄介なものでもある。
顧問先では、社長や部長などの役職廃止、「さん」付けで呼ぶことを推奨している。
「偉い人オーラ」を出して、コミュニケーションの心理的安全性を下げてしまうからだ。
また実力主義の風土という点でもメリットがある。
「部長」と呼んでいた人を、「課長」に降格した場合、本人だけでなく呼ぶ周りの同僚や部下も気まずい。
政治家を「先生」と呼ぶ習慣は、いつからのものか?
(ChatGPT の回答)
1. 教育者としての位置づけ
「先生」という言葉は、もともと「学問を教える人」や「指導者」を意味し、教育や指導の役割を果たす人々に使われてきました。日本では、政治家が国や地域を「導く」存在として、教育者に似た役割を果たすと考えられ、政治家を「先生」と呼ぶことが一般的になったとされています。
2. 幕末から明治時代の影響
この習慣が特に強くなったのは、幕末から明治時代にかけてです。西洋の議会制度や政治の概念を取り入れる中で、議員や政府の役職者が「指導者」や「リーダー」として敬意を込めて呼ばれるようになりました。これにより、議員や政治家が市民や国民を教育し、導く立場にあるという認識が広まりました。
(ここまで)
臥龍も、99%、「臥龍先生」と呼ばれている。
たまに「先生」と呼ばれないときに、かすかな違和感を感じる自分に強烈な違和感を感じてきた。
政治家もそうではないかと想像する。
臥龍の場合は落選はないが、政治家が落選したらどう呼ぶ?
周りも若干、困るような気がする。
臥龍のHPを依頼している担当者に、以下のように臥龍のプロフィールページの微修正を依頼した。
号 臥龍 通称は国内では「臥龍(がりゅう)先生」
を
号 臥龍 通称は国内では「臥龍(がりゅう)さん」*極力「臥龍先生」は避けていただきたい。
に微修正ください。
「臥龍先生」と呼ぶ人にダメ出しはしないが、講演の冒頭で触れておくことは出来る。